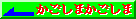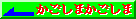


「私の食生活」
私の仕事中の食事は空腹を満たすための作業にすぎない、張り込みに入ったら、
食物を買う時間が無い場合が多い。
時にはまる二日食事をとらないことがある。
事前に買い物をする時間があるときは、弁当は腐るのでパン、ソーセージ、コンビーフなどを
買う、日頃、甘いものは口にしないが、チョコレートなども空腹をしのぐにはいい。
これらのものは全て保存が利くものなので、運良く昼に弁当が買えたり、被調査人が十分大きな
レストランに入った時などは、後の食事にまわす。
ついでに書くがトイレも大きな問題である、男なので小さい方はいいが大きい方は
と言うとそうはいかない。 ワゴン車の後ろで大きなゴミ袋にして捨てるのだ。
ゴミ捨て場に捨ててあるほとんど中身の入ってないゴミ袋を見かけたら気をつけた方がよい。
そう言う仕事をしてるから、プライベートでは食事とトイレにはどん欲である。
ドライブ中にもよおすとパチンコ屋のトイレにははいらずホテルのトイレ、地方では仕方ないので
ファミレスのトイレで我慢する。
食に関しては私は金のあるときと無いときが極端なので一概に言えないが、その時々の予算で
なるべく旨いものを食すようにしている。
そう言うわけで知人から「旨い店をおしえてほしい。」とよくたずねられる。
ただ旨い店というのが曲者で「旨い。」という基準が人それぞれである。
辛党の人もいれば甘党もいるし、好き嫌いもある。
インターネットプレスのスタッフ諸兄からも取材先を教えてほしいといわれるが、
私が思うに10人が10人心から旨いと思う食べ物はなかなか存在しないのである。
また、飲食店の場合 店の雰囲気スタッフの人柄などの要素が加わるので難しい。
だから私は、「旨いかどうか分からないが私の口に合うのは・・・・・です。」
と答えるようにしている。
私の嫌いなタイプの店というのは、「当店は・・・・と・・・・にこだわっています。」と
必要以上に ベタベタと張り紙があったり、親父の講釈がうるさい店である。
そう言った店はまずくはないがそれ以上の感動もない。
「こんなもんだな!」と思うだけである。
逆に、何気なく店に入りさりげなく出された料理にこだわりを発見したときは、とてもうれしい。
真面目に食べ物を商っていれば必然的にこだわりはあってあたりまえである。
最も真面目にこだわっている店は10件中、何件あるだろうか。
私の好きな店の一つに鹿児島市内の豚カツ屋がある。
「かごしまかごしま」の担当者が広告の兼ね合いもあって、「屋号は書かないでくれ。」と
涙ぐんでいるのでここでは伏せるが、実に私の嗜好にあう店である。
無愛想でもなく、だからといって愛想の良い方でもない店主が黙々と豚カツをあげている。
第一印象は普通の店だったが、その豚カツを口に入れたとき、その店のこだわりを感じた。
柔らかい肉は噛むととても豚肉のダシその物の肉汁が口の中に広がる。
それでいて決してしつこくない。
おそらく上質の黒豚であろう、ただそれを示す張り紙など一枚もない。
私は黒豚と言う表記にもいささか疑問を抱いている。
黒だろうと白だろうと良い環境と良い飼料で育った豚はいずれも旨いにちがいない。
黒豚もこれだけはやれば、大量生産でいい加減に育った、ものもいるのではないかとおもう。
詳しくは分からないが、私が食した限り旨くない黒豚も存在するのである。
肉が悪いのか料理人がそれを生かし切れないのか定かではないのだが・・・・・・・
ただその店の豚カツは違う、並ロースかつ定食を注文してもかなりボリュームあるものが
でてくるが、最近少食気味の私でもペロリと入ってしまうのだ、そして腹一杯になり
動くのがいやな状態になっても、胸焼けがしない。
これは明らかに揚げ油だおそらく上質のラードであげているのであろう。
植物油の方があっさりしてそうだがそうではないのである。
植物油は絞ってから時間もたっており常温で野積みにするうちに目に見えない劣化を
起こすのではないだろうか。
反面ラードは生ものとして扱われ保管される融点が低いので常温でも個体であり劣化しにくい
のではないかと思う。
その上芳醇なこくもある。
もしかしたらこの店では豚の脂身からラードを作ってるのではないかとさえ思うほどである。
私は普通豚カツを食すときは飯を2膳たいらげるがそこでは1膳でよい、豚カツだけでも
もたれることなく腹に収まるからだ。
それでいて能書きを言わない店主はすばらしい。
昨日、その店を訪れたときに若い客が、本当に旨かったのだろうガツガツとむせながら
豚カツとエビフライをソースもかけずに食べていた。
「ここはソースも薄味でうまいんだがなぁー。」と思っていると
店主が「ソースも辛くないからかけて食べてごらん。」と話しかけた。
無口な店主の料理に対する愛情を感じた一齣であった。